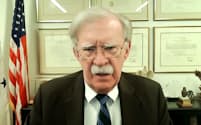安保の核心は行政協定に
帰ってきた日本(18)
日米外交60年の瞬間 特別編集委員・伊奈久喜
安保条約に吉田茂首席全権が実際に署名したことを伝える記事は1951年9月10日付日経1面にある。だが扱いは、予告原稿よりもさらに地味だった。
1面トップではなくワキ扱い。タテ見出しではなく、ヨコ4段であり、「日米安保条約調印す 太平洋の防衛体制確立」とある。
岡崎とラスクに交渉託す
「大軒、木原特派員」とクレジットがつくこの原稿が地味なのは、調印(この物語では実態に合わせて「署名」を使っているが)の事実以外に伝えるべき中身がなかったからだ。当該部分は次のようにある。
「この日米安保条約は前文と本文五カ条から成り、発効には国会に承認を得て政府の批准を要することになっている。同条約には運営実施の細目を規定する『行政協定』が付随することになるが、これは発表されない」
これを読むと、日米間で「行政協定」という名の秘密協定が結ばれたように思える。そうではない。
「日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)」の中身はいまは公表されており、それはまさに「運営実施の細目を規定する」中身である。安保条約署名時に公表されなかったのは、その時点ではまだまとまっていなかったからだ。

行政協定がまとまり、東京で署名されたのは、5カ月後の1952年2月28日であり、署名欄には岡崎勝男、ディーン・ラスク、アール・ジョンソンの3人の名前がある。交渉にあたったのがこの3人である。
この部分だけ、時間が飛ぶのをお許しいただきたい。サンフランシスコ講和条約に署名した51年9月、吉田は首相兼外相だった。官房長官は外務省の後輩、岡崎勝男だった。
行政協定の交渉のため、吉田は51年12月の内閣改造で岡崎を官房長官から未任所国務相にして対米交渉に専念させた。米側はラスク国務次官を大統領特別代表という肩書で大使に任命し、ジョンソン国務次官補が補佐する体制をとった。
ラスクは後にケネディ、ジョンソン政権の国務長官をつとめた。ジョンソンは駐日大使になり、ラスクともども日米関係史にその後も顔を出す。
吉田の回想によれば、行政協定交渉で最も難航したのは第24条だった。まとまった結果の24条は次の通りである。
「第二十四条 日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府は、日本区域の防衛のため必要な共同措置を執り、且つ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議しなければならない」
これがなぜ問題かと現代の読者は思われるだろう。日本の安全保障のために米軍の駐留を認めたのが安保条約なのだから、日本に対する敵対行為や急迫の脅威があれば、日米が共同措置をとるのが当然と考えてしまいがちだからだ。
「ともに守る」発想の芽
だが当時まだ自衛隊はない。警察予備隊の時代である。
にもかかわらず、「共同措置」としたのが、この交渉の成果だったというわけだ。たしかに北大西洋条約機構(NATO)諸国は統帥権を放棄してNATO軍に入り、米国の最高司令官に従うことになっているが、日本にはメンツもあって同じというわけにいかず、岡崎、ラスクで交渉した結果が上の条文である。
この文章にはともに守るという発想の芽がある。それは今日の集団的自衛権をめぐるに議論につながる。
時計の針を51年9月8日のサンフランシスコ講和条約署名直後に戻す。安保条約はまだ署名されていない段階だが、日経は9日付朝刊に「講和に対するわが国の立場」と題する社説を掲げた。
「進んで受諾」と日経社説
社説は講和条約、安保条約の2つを論じる。講和条約にインドとビルマが参加しなかった点を遺憾とし、2国との国交正常化に期待を表明する。
同じく講和に参加しなかった中国について「大陸に中共政権が存在し、台湾に国民政府が残っているという動かし難い事実にもとづいて対処する必要がある」とする。米国は国府、英国は中共を講和条約に参加させるべきだと考えたことは以前もこの物語で触れた。
一方、安保条約については「仮想敵をつくるものであってはならない。そこが日本とその同盟国を明らかに仮想敵とした中ソ軍事同盟と違うところであり、日米安保条約が平和の手段として承認される理由もそこにある」と安保条約のリベラルな解釈を試みる。
余談めくが、「日本とその同盟国」の表現にはやや驚く。日米間で同盟という言葉が使われるのは、大平正芳首相のホワイトハウス発言、レーガン・鈴木共同声明など1980年代になってからだからであり、社説筆者の歴史をみる力を感じる。
社説はこう結ぶ。
「今日の日本がもはや昨日の日本であってはならないということはわれわれの良心である。講和はその良心を事実によって証明する機会を与えるものであり、それであればこそいくつかの不満と不安があっても、今度の平和条約をわれわれは進んで受諾し得るのである」